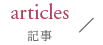グラン・ロゼ
と呼ばれるものは一体どういった姿なのだろう。
セバスチャン・ラパック(文筆家、文学史家、愛飲者)
−La Revue de Vin de France 2016 7/8 記事抜粋
この謎に答えるため、私はマルセイユ行きのTGVに乗った。
途中にある小さな駅サン・シル・シュール・メール(Saint-Cyr-sur -Mer)で下車。そこで私を待っていてくれたのは、プロヴァンスにあるカディエール・ダジュール(Cadière-d’Azur)の隣に位置するバンドール村のシャトー・ドゥ・ピバルノン(Château de Pibarnon)のオーナー、エリック・ドゥ・サンヴィクトール氏であった。

ピバルノンのHPより、奥に地中海を望む 〔ピバルノンはバンドールを代表するトップワイナリーのひとつ〕
彼と二人でラ・シオタの丘の上のレストラン 、ロッシュ・ベルでの待ち合わせに向かう。
待ち合わせの相手はジャン=クリストフ・コモール(Jean-Christophe Comor)氏
グラン・ロゼのエスプリについて思想する人物である。
行けばいつでも幸福をもたらしてくれるプロヴァンス地方
松林や薔薇の色をした家々、瓦屋根、葡萄畑、糸杉、永遠の蒼(あお)をもつ地中海の輝き…
そんな美しさで満たされている。
「プロヴァンスの真髄であった古き時代のロゼワインを再発見することに専念しています。
この地方の葡萄苗はグラン・ロゼの生産に適しているのです。」
話は前置きなしにエリック・ドゥ・サンヴィクトール氏の言葉から始まった。
それに続くジャン=クリストフ・コモール氏
「彼に“マロ”について話してあげなさい。マロ(malos)とはとても大事な用語です。グラン・ロゼが上質であるためには発酵が完了していなければならないのです。マロ、すなわちマロラクティック発酵とはブドウのリンゴ酸と、酵母ではなく乳酸菌による発酵のことで、瓶詰めと出荷の前までにこの発酵が完了するための適度な期間が必要なのです。つまり収穫年の12月くらいでは、瓶詰め、出荷にはまだ早すぎるのです。」
夏になると商品陳列棚にずらりと並ぶ大手製造社のロゼ達、悲しいことにこれらは発酵段階で正しいケアを受けていないのが現状である。
人気が伸びてきているロゼ
流行に乗りブルゴーニュではピノ・ノワール種で、バスク地方ではタナ種でも作られるようになった。また南西部のモントーバン( Montauban)付近ではネグレット種、ルシヨン地方(Roussillon)ではグルナッシュ種が用いられる。
〔ここで紹介のバンドール シャトー・ドゥ・ピバルノンのロゼは、ムールヴェドル種が主体〕
いくつかの地域では、ラベルに「ロゼ」と表記するが、一方でそれをしないワイナリーもある。色について言うと、サーモン色から鮮紅(せんこう)色、玉ねぎの皮の色まで様々であり、その時々の発酵の気の向くままに変化する。ロゼワインの色合いは、マーケティングの専門家によって日々研究され選ばれている。派手めでキラキラと輝くような色合いのロゼは若い世代に人気がある。
ルビー色にきらめくシャトー・ドゥ・ピバルノンのキュベ2015「ニュアンス」をエリック・ドゥ・サンヴィクトール氏、オーナー自ら味見する。
大樽と素焼きの壺の中で醸造される彼のワインからは、まるで古代の歴史がよみがえったかのようだ。シャトー・ドゥ・ピバルノンのキュベ2014は、夏の真っ盛りではなくて、霧深い冬の日に飲まれることをお勧めしたい。
これもひとつグラン・ロゼを発見する方法なのである。
“Eric de Saint Victor goûte les rosés nés d’histoires anciennes,
non d’élucubrations mercantiles.”
ロゼワインは伝統・文化・歴史から生まれた。コマーシャル理論からではなく・・・
“LA REVUE DU VIN DE FRANCE ” No.603 2016, 7/8月号より記事抜粋
www.larvf.com.
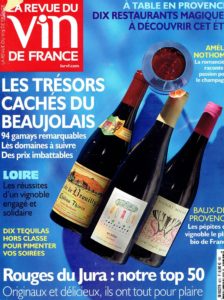

ローヌ&プロヴァンスワインの店
aVin